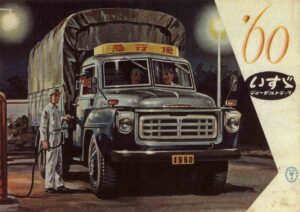最近、「小規模分散型水道」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
特に2024年の能登半島地震以降、「災害に強い水道」を求める声とともに、この「小規模分散型水道」というキーワードがさまざまな場面で使われるようになってきています。こうした言葉が注目される背景には、これまで進められてきた「水道の広域化」に対する一定の反省や見直し機運があると感じています。
ただし、筆者はここで一つ、ソフトな形で注意喚起をしたいと思います。
それは、「小規模」「分散」といった言葉の印象に引っ張られ、「小さいこと」や「個別であること」自体が良いと短絡的に受け取られてしまうリスクです。この記事では、小規模分散型水道の背景や意味を改めて見直しながら、水道の在り方の本質について考えてみたいと思います。

小規模分散型水道という言葉が登場した背景
「小規模分散型水道」という言葉は、まだ明確に制度や法律で定義された用語ではありません。
近年の自然災害、特に能登半島地震において広域にわたる断水が発生したことが、この言葉の浸透を後押ししたと思われます。
実際、これまでの水道行政は、水道の広域化・大規模化の方向で進んできました。これは、日本が直面する人口減少という長期的な課題に対応するため、管理拠点を減らして維持管理コストを削減しよう、という合理的な取り組みでもありました。また、実際、この取り組みによって、ランニングコストと管理負荷の低減を実現を達成した実例もあり、この取り組み自体は問題ではないと考えます。
一方で、広域化された水道システムの中核をなす浄水場が、地震などの災害で被災すると、広範囲にわたる断水リスクをはらむという課題が指摘されてきました。こうしたリスクが、2024年の能登地震という具体的な事例で顕在化したことにより、その反動として「小規模分散型水道」が注目を集めている構図です。
小規模・分散の意味は?定義はまだ曖昧
「小規模分散型水道」という言葉が頻繁に使用されていますが、その規模感や適用範囲に関する明確な定義は2025年5月現在存在しません。1軒単位の独立水源から、数軒〜数十軒をカバーする集落規模のものまで、さまざまな解釈が混在しています。あるいは雰囲気だけで使用しているようにも見えます。
言い換えれば、「小規模分散型」と一言で言っても、実際に何軒の世帯を対象としているのか、どのような技術や体制で運用されるのかは、ケースバイケースであり、統一的なモデルは存在しないということです。
このままでは、「とにかく小さければよい」「とにかく分散していれば安心」という短絡的な認識につながりかねません。これこそが、筆者が警鐘を鳴らしたいポイントです。
小規模が有効な場所と、そうでない場所
水道の広域化が適正だった地域があるように、小規模分散型水道が真価を発揮する場面があります。
たとえば、限界集落のように、人口が数軒〜数十軒にまで縮小した地域では、大規模な浄水施設や長大な配水管網にこれらのエリアを組み込み、将来にわたって昨今の問題の配管を維持するのは非現実的です。こうした地域では、現地の井戸や小型の浄水装置による簡易な給水システムが、低コストで効率的な水道システムと考えられます。
しかし、都市部にこの考え方をそのまま持ち込むと、現実的ではなくなります。
たとえば、東京都内で「1000m四方ごとに1施設の浄水設備を設けて分散管理する」とした場合、膨大な初期コストと維持費がかかるばかりか、人材確保の面でも非現実的です。大都市圏では、ある程度の規模と集約性がなければ、水道事業の運営は成り立ちません。
要するに、水道の適切な「規模感」は、その地域の人口や地理的条件、災害リスクに応じて最適化されるべきであり、「広域化」か「小規模分散化」かという二項対立で語るべきではないのです。
流行語に踊らされず、土地ごとの最適解を
筆者は、「小規模分散型水道」や「水道の広域化」という言葉そのものを否定するつもりは全くありません。むしろ、「小規模分散型水道」については、これまでの画一的な広域化一辺倒の議論を見直すきっかけとしては非常に意義深いと感じています。
しかし、注意すべきはその「流行り方」です。災害の記憶が生々しい今だからこそ、「小規模」「分散」といった言葉が心に響きやすく、その響きのよさゆえに、十分な議論や検証を経ずに導入が進んでしまうことへの懸念を抱いています。
水道の形は、地域ごとの実情に応じて決まるべきです。人口密度、地形、水源、維持管理体制、災害リスク――あらゆる条件を冷静に整理し、それぞれの土地にとってもっとも「現実的で持続可能なスケール」とは何かを見極める必要があります。
結論:「小規模分散」は目的ではなく、手段のひとつ
今、「小規模分散型水道」という言葉が注目されていますが、その背景には、これまでの「水道の広域化」への反発的な空気があることも否定できません。
しかし、言葉に振り回されてはいけません。水道のあるべき姿は、その土地土地の条件に合わせて柔軟に設計されるべきものです。
筆者は、「小規模分散型水道」という言葉に込められた期待を理解しつつも、あくまでそれは手段のひとつであり、目的は『持続可能で災害に強い水道』であるべきだと考えます。
流行語ではなく、地域ごとの最適解。それを見極める眼差しこそ、いま私たちに求められているのではないでしょうか。