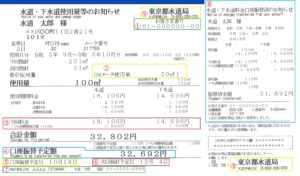― “飲める蛇口水” が当たり前ではない理由 ―
世界で、水道水をそのまま飲める国はわずか 12 ヵ国(WHO 2023)。
日本はその貴重な一員です。それでもペットボトルや浄水器が売れ続けるのはなぜでしょうか。
本稿では、日本の水道が持つ強みと課題を、世界との比較を交えながら整理します。

まず数字で把握:日本の水と世界の水
| 指標 | 日本 | 主要先進国平均* | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 人 1 日水使用量 | 250 L | 200 L 前後 | 国交省 2023 |
| 水道水質基準項目数 | 51 項目 | 30〜40 項目 | 厚労省/WHO |
| 飲用可能な水道国家数 | 12/195 | — | WHO 2023 |
* 主要先進国=OECD24 ヵ国平均(2022)
2. なぜ日本の水道は飲めるのか
- 法定 51 項目の水質基準
- WHO ガイドラインより厳しい項目も多い。
- 浄水場の多重バリア
- 急速ろ過+オゾン+活性炭=高度浄水処理比率 70 %(政令市平均)。
- 残留塩素 0.1 mg/L 以上を義務化
- 配水管末端でも菌増殖を抑制。
- 目標値は0.3mg/L
2000 年以降、日本で水道水が原因の集団健康被害は報告されていません(厚労省 水道統計 2024)。
3. それでも「ペットボトル」「浄水器」が選ばれる3つの理由
| 要因 | 具体例 |
|---|---|
| 味・臭い | 過去のダム湖の藻類由来臭苦情問題、古い配管の金っぽさ(自宅の古い配管が原因) |
| 不安心理 | SNS の PFAS/PFOS 報道、震災断水体験 |
| ライフスタイル | 持ち歩きボトル需要、コーヒー・紅茶の味こだわり ペットボトル水を持ち歩くスマートさが評価された時期があった |
4. “当たり前の水” が止まる瞬間
- 2019 年長野・千曲川氾濫
下水処理場冠水 → 上水も 3 か月断水。 - 2024 年能登半島地震
送配水管 900 か所以上破損、困難地域以外の水道全面復旧までに 約3か月 - 首都直下地震想定
最大 1,100 万人断水/5 日後も 300 万人(内閣府 2022)。
災害時は「飲める水道」が 1 日で“飲めない・出ない水道” になる。
このギャップを埋めるのが家庭備蓄と災害給水ステーションです(近日中に詳述)。
5. まとめ
- 日本の水道は品質・安全面で世界トップクラス。
- とはいえ「水道は危険・まずいはず」という心理的不安からペットボトル・浄水器需要は今後も続く。
- 「飲める水」が 永続保証ではない と知り、備蓄や節水術を併せて考えることがご家庭でできる現実的な防災となります。